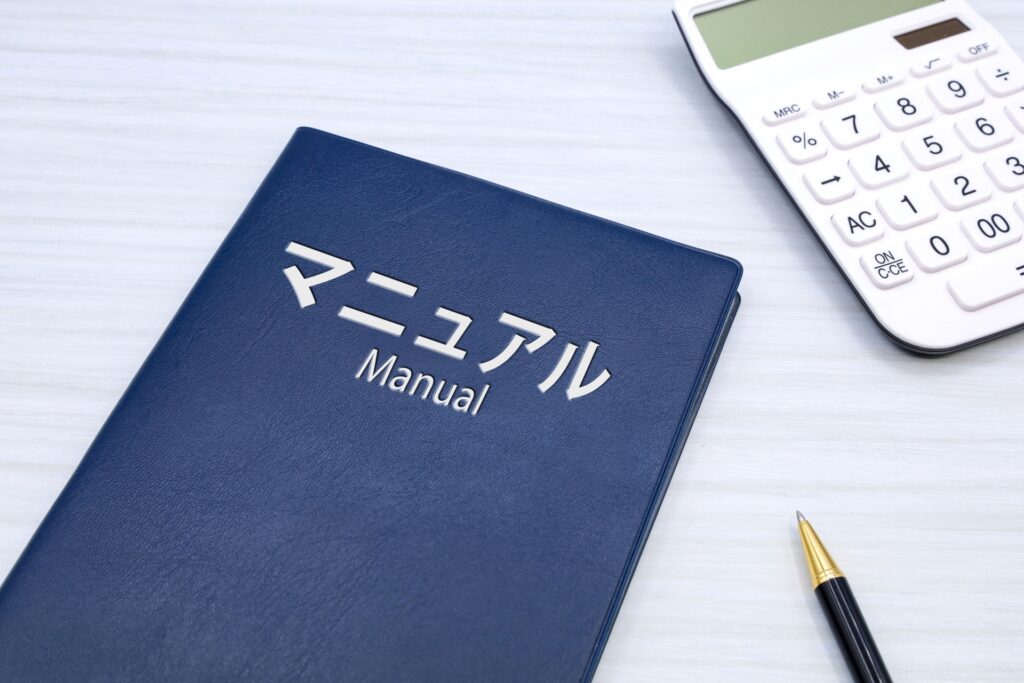
社史・年史・記念誌の制作には多くの工程が関わるため、「何から始めればよいのか分からない」という声も少なくありません。
本記事では、準備・企画構成から制作・印刷・配布まで、社史制作の全体像を5つのステップに分けてわかりやすく解説します。
初めて制作を担当する方にも理解しやすいよう丁寧にまとめました。ぜひご覧ください。
1 準備
1-1 基本方針の策定
まずは「なぜ社史を作るのか」の目的を明確にします。
また、「発行時期」や「媒体(冊子・デジタル等)」、「予算」、「配布対象」などの条件も整理します。
・経営戦略や変革の歩みを記録・共有し、将来の意思決定に活かす
・自社および業界に関する資料を体系的に整理・保存し、社会的資産とする
1-2 制作体制の整備
円滑な進行のために、社内に担当部署や編纂委員会などのプロジェクトチームを組織します。
また、外部の制作会社に依頼する場合は、この段階で検討します。
これが不明確なままだと、最終段階で内容の修正や方針変更が発生し、制作全体に大きな影響を及ぼす恐れがあります。
2 企画・構成
2-1 基本企画の決定
一般的に社史は以下のように構成されます。
まずはこのような大きな区分を決めます。
| 区分 | 内容の例 |
| 前付 | 表紙、序文、代表者等の挨拶文など |
| 口絵 | 写真ページ、ビジュアル年表など |
| 本文 | 沿革、特集記事など |
| 後付 | 資料(年表、組織図、業績推移等)、索引、奥付など |
次に、この中でも中心となる「本文」について、より詳細な構成案を検討します。
本文の構成にはいくつかのタイプがあり、たとえば次のような例が挙げられます。
・創業から現在までの歴史を網羅的に記録するタイプ
・直近20年など、特定期間にフォーカスするタイプ
・主力製品・サービスの変遷や、歴代社長の取組といったテーマ別の構成とするタイプ
2-2 特集企画の決定
社史・年史・記念誌では、過去の出来事を時系列に沿って整理・記録するのが基本ですが、それに加えて、読み応えのある特集記事を設けることで、誌面に厚みと個性が生まれます。
たとえば、創業者の思いや経営理念を深掘りする特集、現場社員による座談会、未来へのビジョンを語るインタビューなど、企業・団体の特色や価値観を伝える企画が効果的です。
2-3 構成案(仮目次)の作成
「2-1 基本企画」や「2-2 特集企画」の内容がある程度固まった段階で、掲載順や章立てなど、社史全体の構成案(仮目次)を作成します。
これにより、制作全体の見通しが立ちやすくなり、関係者との認識共有にも役立ちます。
たとえば、1ページあたりの文字数や写真点数の目安が決まっていれば、「3-3 原稿の執筆・リライト」の際に、あらかじめ分量を意識した原稿作成が可能となります。
2-4 制作スケジュールの策定
発行時期をもとに逆算し、原稿作成、レイアウトデザイン、印刷など、各工程のスケジュールを具体的に設定します。
特に社内確認や経営陣の承認には時間を要することが多いため、余裕を持った計画が不可欠です。
特に、「誰が」「何を」「いつまでに」行うかを具体的に定めることが、スムーズな進行のカギとなります。
2-5 製本スタイルの検討
配布対象や保存性、発行目的に応じて、印刷・製本の仕様を検討します。
「記念品としての保存性を重視するか」「手に取りやすさや軽さを優先するか」など、用途に応じた判断が必要です。
・装丁の形式(上製本[ハードカバー]/並製本[ソフトカバー])
・判型(A4、B5、正方形など)
・用紙の種類(本文用紙・表紙用紙の質感や厚み)
・印刷方式(オフセット印刷/オンデマンド印刷)
・カラーページの比率(全ページカラー/本文モノクロ+口絵カラー)
・表紙加工(箔押し、PP加工、布張りなどの装飾)
3 制作
3-1 資料の収集
社内に保管されている記録文書、報告書、社内報、写真、動画など、過去の資料を収集・整理します。
必要に応じて、業界団体や図書館、新聞社など外部機関が保有する資料の調査も行います。
なお、この段階では、どの資料・写真が必要かはまだ明確でないことが多いため、「使えるかわからない資料」も含めて、幅広く集めておくことが重要です。
3-2 基礎年表(時系列表)の作成
企業・団体の歩みを時系列で整理し、主な出来事を一覧化します。
この年表は、社史全体の骨格をつくる作業であり、情報の過不足がないか、事実が正確に整理されているかが重要です。
その後、一覧化した出来事に対して、重要度に応じたランク付け(A・B・Cなど)を行い、Aランクに位置づけた項目を社史・年史・記念誌の本文に採用する流れが一般的です。
3-3 原稿の執筆・リライト
資料やインタビューをもとに、本文や特集記事の原稿を執筆します。社内メンバーが下書きを作成し、それをもとに制作会社が読みやすく整え、用語や文体を統一するリライトを行うのが一般的です。
執筆に適した社内メンバーがいない場合は、プロのライターに依頼することで、文章の品質や客観性を高めることも可能です。
3-4 デザインの作成(組版・レイアウト)
表紙デザインおよび中面のデザインを制作し、その後、「3-3 原稿の執筆・リライト」で作成した原稿を誌面に流し込みます。
方向性が未決定の場合は、この工程でデザイン案を検討する必要があります。一般的には、デザインの方向性は構成案策定と並行して、早めに固めておくのが望ましいです。
3-5 校正・校閲の実施
レイアウト済みの原稿をもとに、誤字脱字の修正はもちろん、固有名詞や数値の誤記、文脈の整合性などを丁寧に確認します。
社内関係者による内容チェックも含め、通常は2~3回の校正を重ねながら精度を高めていきます。
万全を期したい場合や重要度の高い内容を含む場合は、第三者視点でチェックができる校閲会社の活用も有効です。
3-6 社内確認と最終承認
完成した原稿について、経営層や関係部門からの最終承認を得ます。
社史・年史・記念誌は企業の対外的な印象にも関わるため、事実関係や表現内容について慎重な確認が不可欠です。誤りのない形で決定し、印刷工程へと進みます。
そのため、「1-2 制作体制の整備」の段階で、プロジェクト責任者や担当役員を明確にし、報告・承認の流れをあらかじめ整えておくことが重要です。
また、制作の各段階で、段階的に確認・承認を得る体制を構築しておくと、最終確認がスムーズに進みます。
4 印刷
4-1 色校正の実施
印刷前に、色味や仕上がりを確認するための試し刷り(色校正)を行います。
表紙や写真ページの発色、文字の見え方、紙との相性などを確認・調整し、最終的な印刷データを確定させます。
4-2 印刷・製本の実施
確定した仕様に基づき、本番の印刷と製本を行います。
印刷所とのスケジュール調整や納品日の管理も重要な作業です。特に周年行事や式典などと連動する場合は、納期厳守が必須となるため、進行管理には細心の注意を払いましょう。
5 納品・配布
完成した冊子は、社内外の関係者、取引先、地域機関などに配布されます。
配布にあたっては、封入・発送作業や宛名リストの管理などが必要になる場合もあります。
また、PDF化したデータをイントラネットやWeb上で公開し、広報資料や採用ツールとして活用するケースも増えています。
