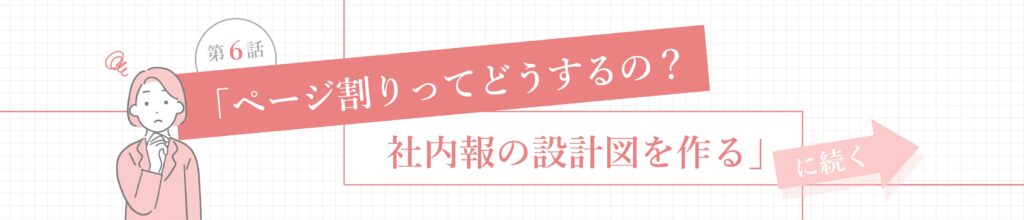アイデアは出るけれど選べない
いよいよ具体的な社内報作りがスタートしました。まずは記事の企画から。メンバーから次々とアイデアが飛び出します。
「社員の趣味を紹介するコーナーはどうだろう」
「休憩スペースで撮った面白写真を集めるのも面白そう」
どれも魅力的な企画ばかり。でも、果たしてどれが社内報にふさわしいのでしょうか。読者の関心を引きつけられるのは、どんな記事なのか…。
アイデアを出すだけなら簡単だけど、本当に読んでもらえるコンテンツは何なのか。限られた紙面の中で、何を優先して伝えるべきか。社内報らしさを大切にしつつ、読者の心に響く記事を作りたい。
改めて、社内報の在り方について考えさせられます。
「会社の状況を知りたいという社員の声は多いから、社長インタビューは絶対に外せないよね」
「新入社員紹介は、その人となりが伝わるように工夫したいな。プライベートな面も掘り下げてみよう」
「お家時間の過ごし方は、リモートワークで家にいる時間が長い人も多いから、参考になりそうだね」
議論を重ねるうちに、徐々に社内報らしい企画が見えてきました。
情報と共感、その両方を大切にする紙面作り。
社員に寄り添い、社員をつなぐメディアとしての方向性。
手探りながらも、編集チームの目指す道筋が定まっていったのです。
読み手の立場に立って、何を知りたがっているのかを考える。そこから企画を組み立てていく、そんな姿勢が大切なのだと実感するのでした。
他社の事例を見て、ヒントを得る
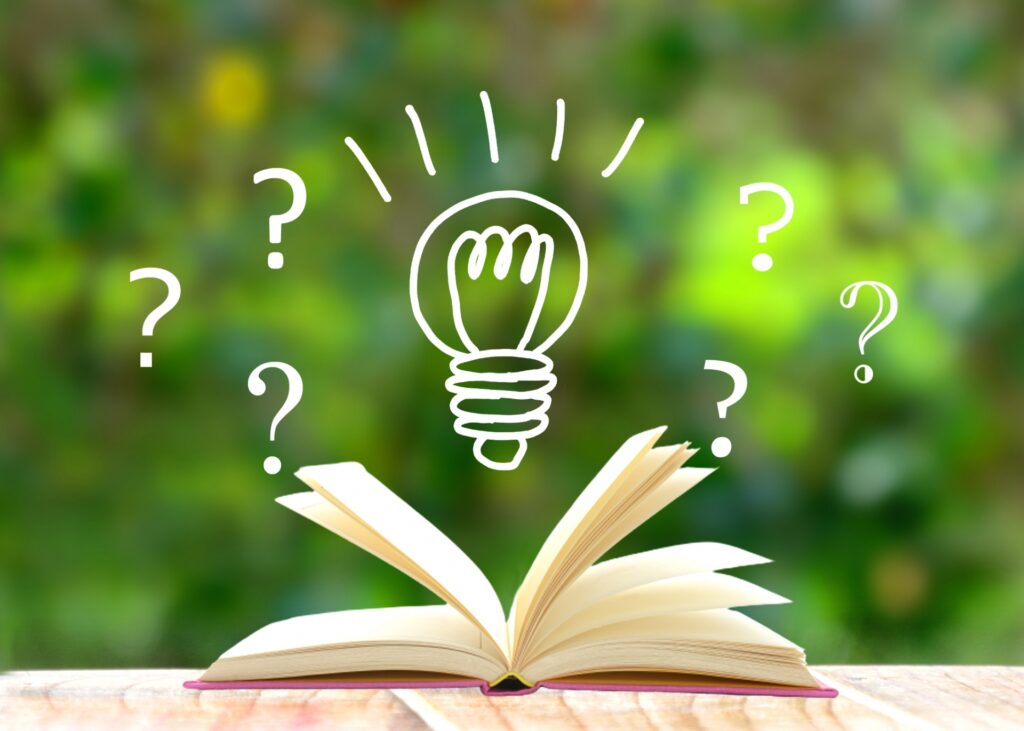
さらに、よりよい企画を求めて、他社の社内報を手に取ってみることにしました。先人の知恵に学べば、きっと私たちの道も開けるはず!
「他社の社内報を読んでみたら、思いのほかバラエティに富んでいて驚いたよ」
「情報量も多いけど、遊び心も感じられる。参考になるね」
実際に手に取ってみると、そこには学ぶべき点がたくさんありました。硬い内容も、読者の目線に立って柔らかく伝える。楽しさと情報量、そのバランス感覚が秀逸だったのです。
「どの社内報も、自社らしさを大切にしているのが伝わってくるね」
「うちの場合は、どんな切り口で勝負するべきなんだろう」
「アットホームな雰囲気は、うちの社風そのもの。それを全面に出していけばいいのかも」
他社の事例を研究していくうちに、編集チームにも新しい視点が生まれてきました。
写真や図版の使い方、記事と記事の間にちょっとした遊び心を入れ込むアイデア。
他社の社内報を研究するほどに、やるべきことが見えてきます。
さらに、これらを単に真似るのではなく、自分たちなりのやり方を模索すること。そこから生まれるオリジナリティこそが、私たちの社内報の命なのだと気づかされるのでした。
コロナ禍ならではの企画にフォーカス
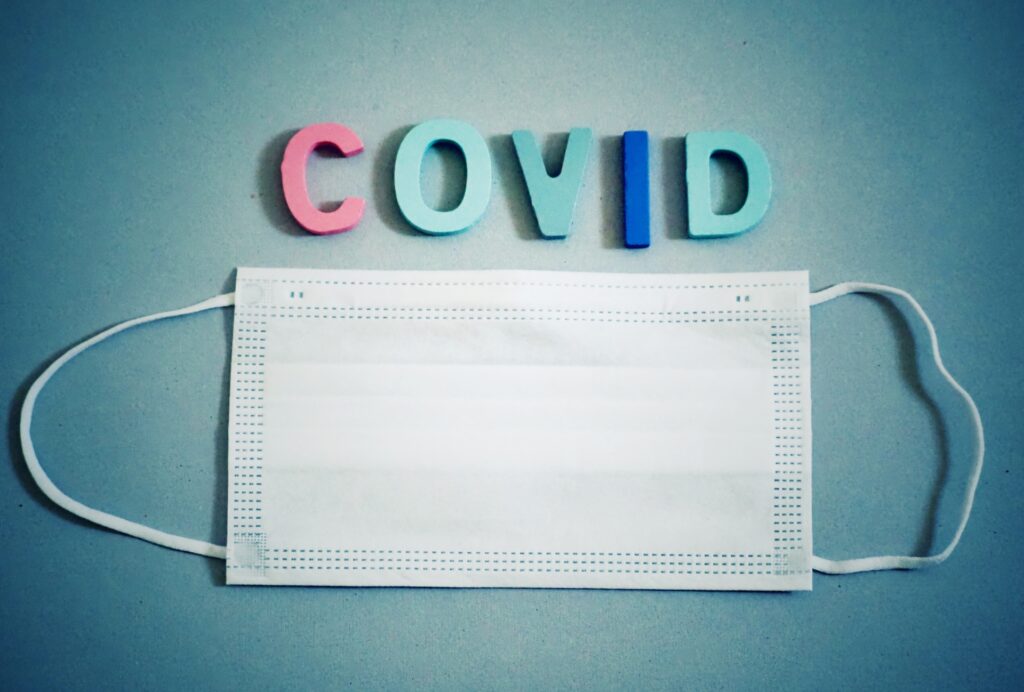
他社の事例研究と並行して、社内報の方向性を探る日々が続きます。
模索の中で見えてきたのは、コロナ禍という特殊な状況への向き合い方でした。
「コロナ禍で先の見えない不安を抱える社員は多いはず。そんな時だからこそ、会社の今を伝える社長インタビューは意味があるんじゃないかな」
「そうだね。社長の言葉で、社員を勇気づけられるかもしれない」
「オフィスに出社する機会が減って、同僚との交流が減っているのも問題だよね。新入社員紹介で、コミュニケーションのきっかけを作るのはどうだろう」
普段は感じることのない不安や孤独。そんな社員の心情に寄り添うべく、私たちはコロナ禍ならではの企画を軸に据えることにしました。
マイナスをプラスに変える発想の転換。ピンチをチャンスと捉え直す視点。そんな企画を通して、社員同士のコミュニケーションを活性化させるという私たちなりのスタイルが見え始めたのです。
「不安を和らげ、孤独を紛らわせるような、心温まる紙面を目指そう」
「『会社は社員の味方』というメッセージを込めたいよね」
「苦しい時期だからこそ、社内報で社員同士のつながりを感じてもらえたら嬉しいな」
こうして編集チームでは、コロナ禍に立ち向かうための企画アイデアが続々と生まれました。
各社員のおすすめのお家時間の過ごし方を共有し合えば、息抜きのヒントになるかもしれません。リモートワークで感じるストレスの解消法を特集すれば、同じ悩みを抱える社員の支えになるはず。
企画の方向性に悩んでいたはずが、いつしか前向きな企画が溢れ出していました。
「そういえば、コロナ禍での新しい働き方についての記事もいいかもしれないね」
「テレワークのコツとか、オンライン会議の活用法とか、役立つ情報がありそう」
「withコロナ時代を乗り切るためのヒントを、社内報から発信していけたらいいよね」
次々と湧き出るアイデアに、編集チームの意欲もかき立てられます。
社員の生の声を拾いながら、ニーズに応える企画を練っていく。読者の立場に立って、真に必要とされる情報を見極める目を養っていく。
創意工夫を凝らし、新しい形を模索し続けることが大切なのでしょう。