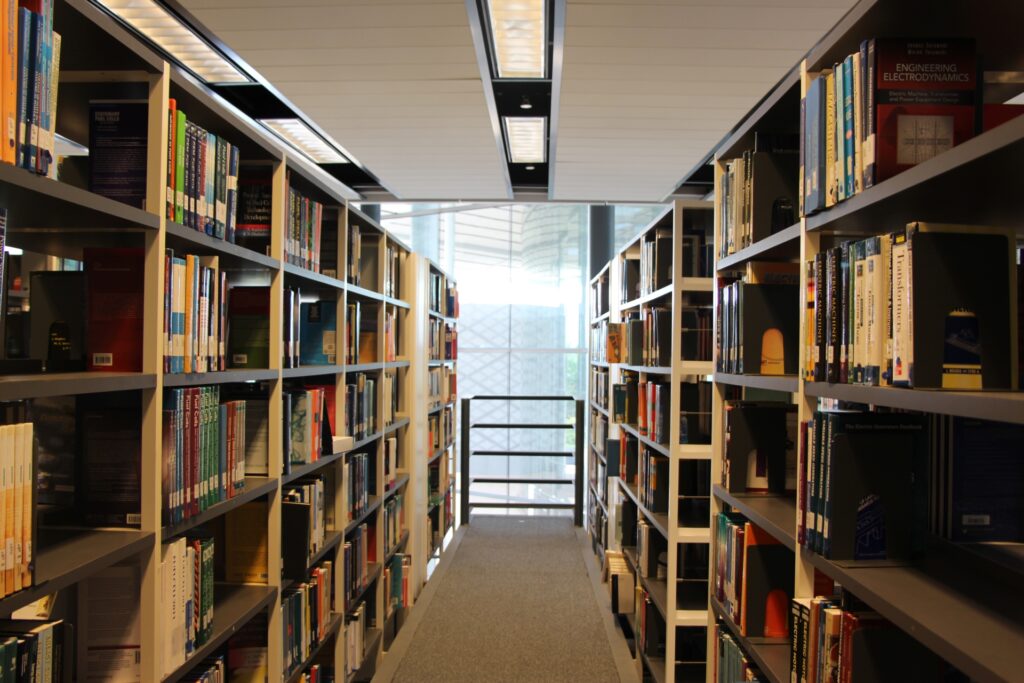
社史や年史、記念誌は、どうしても社内向けの資料と見なされがちです。しかし実際には、研究者や学生、地域社会、産業界の皆さまなど、さまざまな立場の方々にとって貴重な情報源となり得るものです。
せっかく多くの時間と労力をかけて編纂したのであれば、より広く活用していただくためにも「寄贈」という選択肢を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
本記事では、社史や年史、記念誌を寄贈する意義や、その具体的な寄贈先について紹介します。
社史は社外でも利用される
社史は、企業研究を行う研究者や学生にとって、重要な一次資料となります。
また、社会学・経済学・経営学などの学術領域においては、特定産業や地域経済の研究を深めるための貴重な文献としても扱われることが多いです。
社史のおススメ寄贈先
では、実際に社史や年史、記念誌をどちらへ寄贈するとよいのでしょうか。ここでは、いくつかの代表的な寄贈先をご紹介します。
1. 国立国会図書館
国立国会図書館は、日本国内で出版されたすべての出版物を収集・保存することを目的とする国内最大規模の図書館です。
法律により、出版社や発行者は国会図書館に刊行物を納本する義務(いわゆる「納本制度」)を負っており、これらの資料は長期的に保存・管理され、研究者や一般利用者が閲覧可能となります。企業が独自に編纂・発行する社史や年史、記念誌も“出版物”として扱われる場合があります。
2. 県立川崎図書館
県立川崎図書館では、「社史コレクション」として国内有数の資料を所蔵しており、その量と質において全国的に見ても大変充実しています。
これらの資料はどなたでも自由に書架から手に取れるため、地域住民や研究者が日々、調査研究に訪れています。これほど多くの社史類を扱いやすい形で提供している例は珍しく、県外からも多くの方が足を運ばれるそうです。
3. 研究機関(例:東京大学経済学部図書館)
大学の付属図書館や学部図書館は、専門分野に特化した資料を収集しており、研究者や学生が学術活動を行う上で欠かせない情報源を提供しています。
なかでも、東京大学経済学部図書館のような経済・経営分野に注力する機関は、企業資料のコレクションにも力を入れているため、こうした場所へ寄贈すれば、実務的・学術的観点のいずれからも高い価値をもたらすでしょう。
https://www.lib.e.u-tokyo.ac.jp/?page_id=613
※寄贈にあたっては、必ず事前連絡をお願いします。
4. 関連業界の団体・研究機関
製造業であれば業界団体、サービス産業であれば関連協会など、企業が属する業界には多くの場合、専門団体や研究機関が存在します。
これらの機関は業界全体の歴史や資料を収集・保存し、会員や一般向けに情報を発信しています。そのため、社史や記念誌を寄贈することで、同業界内の研究や活性化に貢献することができます。
機密情報保護や個人情報保護の観点から無暗な寄贈は控える
最後に注意点です。
寄贈を行う前には「機密情報」や「個人情報」の取り扱いを慎重に確認しましょう。社史や年史、記念誌には、企業秘密に関わる売上推移や製品開発の詳細、あるいは特定の社員の個人情報などが含まれる場合があります。
外部公開を想定していない情報をそのまま掲載してしまうと、競合他社に対する情報漏洩や、法的リスクにつながりかねませんので、無暗な寄贈は控えましょう。
大切に編纂した社史や年史、記念誌が、未来の研究者や地域の皆さまの目に触れ、企業の歩みをより多くの方々と共有できるとしたら――それは企業が長年積み上げてきた努力や想いを、社会全体に還元する大きな機会となるでしょう。
この機会に、「社史や年史、記念誌を寄贈する」という選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。そうすることで、企業の歴史がより多くの場面で生き、さらなる価値を生み出していくはずです。
