
「会社で社史担当になったものの、右も左もわからない…」 そのような悩みを抱えてはいませんか?
日本屈指の社史コレクションを保有する神奈川県立川崎図書館は、社史について調べたいときにぜひチェックしておきたい場所としても知られています。
そこで今回は、筆者が実際に訪れたときの経験も活かしながら、その魅力に迫っていくことにしました。もちろん、活用方法や利用方法についても紹介。一緒に、神奈川県立川崎図書館「社史コレクション」への扉を開いていきましょう。
1. 神奈川県立川崎図書館とは
まずは神奈川県立川崎図書館について知っておきましょう。ここでは、概要や基本情報、アクセスなどについて紹介していきます。
1.1. 神奈川県立川崎図書館の概要
神奈川県立川崎図書館は、もともと「ものづくり技術」を支える分野に特化した図書館として1958年に開館しました。
それと同時に社史の収集もスタートさせ、年々コレクションは増加。今では経済団体史なども含み、所蔵する社史は2024年2月時点で約22,000冊となっています。
まさに、「日本屈指の社史コレクションを保有する図書館」と言えるでしょう。
1.2. 神奈川県立川崎図書館の基本情報
神奈川県立川崎図書館の基本情報は、以下の通りです。
〒213-0012 川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西棟2F
■ 電話番号
044-299-7825
■ 開館時間
月~金:9時30分~19時30分 / 土・祝休日:9時30分~17時30分
■ 休館日
日曜日(祝日の場合を含む)、 毎月第2木曜日(祝休日にあたるときは翌金曜日)/ 年末年始・資料総点検期間
■ 公式サイト
URL:https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/
なお、公式サイトには神奈川県立川崎図書館の開館日カレンダーが掲載されており、詳しい開館情報が得られます。特に注意しておきたいのが、資料総点検期間です。「訪問したら、今日は閉館日だった…!」なんてことがないよう、事前にしっかり情報をリサーチしておきましょう。
1.3. 神奈川県立川崎図書館へのアクセス
神奈川県立川崎図書館は、かながわサイエンスパーク(KSP)という建物の中に入っています。かながわサイエンスパーク(KSP)までは、電車やバスなど公共交通機関でアクセスすることができます。
JR 武蔵溝ノ口駅より徒歩15分、東急田園都市線・大井町線 溝の口駅より徒歩15分
■川崎市営バス
「高津中学校入口」下車 徒歩1分
また、KSPシャトルバスも運行しており、溝口駅北口バスターミナルから乗車可能。ただし、平日の10時00分前は会員専用のバスとして運行されているようなので、乗車可能時間を見計らって利用する必要があります。
一方、車や自転車の場合、図書館専用の駐車場や駐輪場はないので、
かながわサイエンスパーク(KSP)の地下駐車場(有料:100円/20分)
■駐輪場
敷地内にある駐輪場
を利用しましょう。アクセス面で優れている点も、嬉しいポイントのひとつです。
2. 訪れる際はまず予習から

日本屈指の社史コレクションに対し、「敷居が高そう」「いきなり訪れても大丈夫かな」と不安を感じることもあるでしょう。そのようなときには、訪れる前に予習しておくと安心です。公式サイトでは、予習に役立つ3つのコンテンツが紹介されています。
・すごい社史
・バーチャル社史室
では、ひとつずつ見ていきましょう。
2.1. 「社楽~SHARAKU~」で知識を深める
「社楽~SHARAKU~」は、神奈川県立川崎図書館が発行している社史情報史です。
参考)公式サイト「社楽~SHARAKU~」
神奈川県立川崎図書館が保有する社史コレクションをさらに活用してもらうためにできた広報誌なのだそう。公式サイトでは、バックナンバーもすべて閲覧できます。2012年6月に記念すべき第1号を発行し、2025年1月にはなんと第107号を発行。歴史の長さを感じずにはいられません。
社楽では、社史の使い方や楽しさ、社史に関する情報を様々な切り口から紹介しています。思わず「へぇー!」と感じるものや、社史の調査時に役立つ実用的な情報も紹介されており、まさに「予習」に役立つコンテンツと言えそうです。
2.2. 「すごい社史」で注目作をチェック
次に見ておきたいのは、「すごい社史」です。
参考)公式サイト「すごい社史」
ここでは、特色を持つ社史が写真や簡単な説明とともに説明されています。現在公開されている社史は171冊(2025年2月時点)。社史を閲覧するときに、注目しておきたいポイントなどを知ることができます。気になる社史があったら、ぜひ資料名や企業名をメモしておきましょう。社史コレクションで実際に手に取り、深掘りするのも面白そうです。
また、写真を通して社史の表紙がチェックできる点も、魅力のひとつ。通常、社史は書架に並んでいる状態なので、背表紙しか見えません。このコンテンツでは表紙が閲覧できるため、デザインや雰囲気づくりの参考にもなりそうです。
2.3. 「バーチャル社史室」で空間をイメージ
最後は「バーチャル社史室」で、社史コレクションのイメージをつかみ取っていきましょう。
参考)公式サイト「バーチャル社史室」
ここには、社史コレクションの書架を撮影した写真が掲載されています。社史コレクションの書架を自宅から眺めているような感じです。貸出中のものや書庫などに保管されているものもあるため、「全く現状と同じ」という訳ではありません。しかしながら、社史コレクションの雰囲気を感じ取るには十分でしょう。
3. いざ!社史コレクションの世界へ
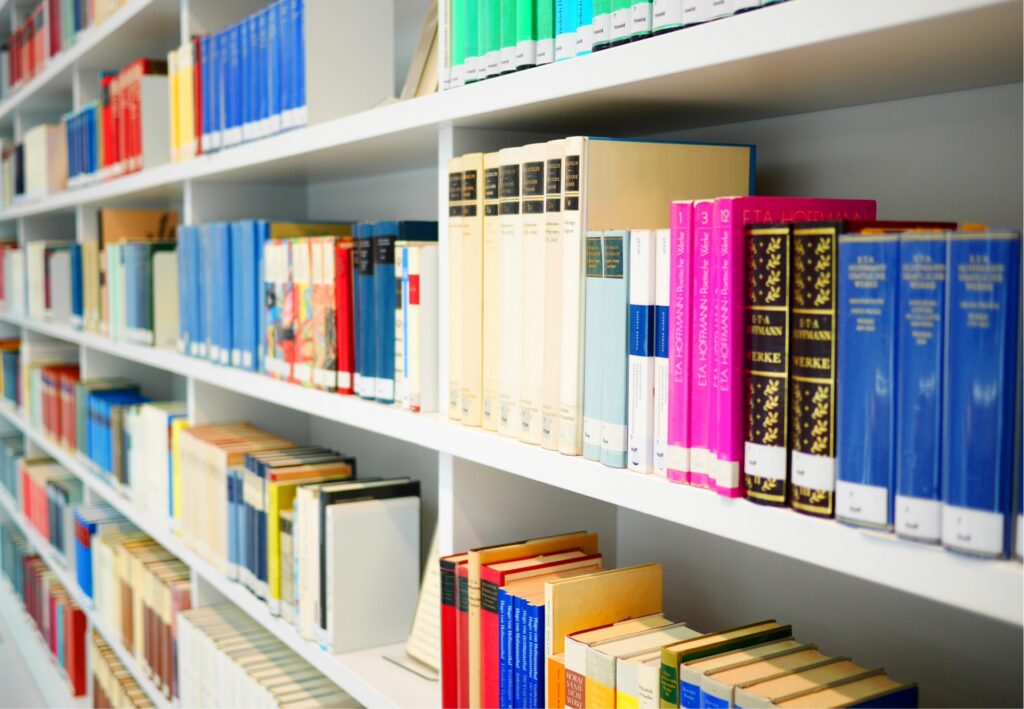
予習が済んだら、いよいよ神奈川県立川崎図書館「社史コレクション」の世界へ足を踏み入れてみましょう。まず訪れたいのは、メインとなる社史コーナーです。ここでは、社史コーナーの紹介はもちろんのこと、活用方法などにも触れていきます。
3.1. まずは社史コーナーへ
図書館に入って奥に進んで行くと、右側のエリアに社史コーナーが見えてきます。人の出入りが少なく、他と比べても一段と落ち着いた雰囲気が漂っています。社史が整然と並べられている書架からは、凛とした美しさも感じられるでしょう。
社史は、建築・土木・不動産…といった具合に、業種ごとに細かく分類された状態で書架に並んでいます。書架にない社史に関しては、「大型本コーナーにあります」「書庫にあります」といった案内表示パネルもあり、とてもわかりやすいです。まずは社史コーナーの全体像をつかむために、グルっとひとまわりしてみましょう。コレクションの豊富さに驚かされます。
3.2. 社史を比べて違いを知る
気になる社史を見つけたら、ぜひ実際に手に取ってみてください。できれば2冊以上がおすすめです。なぜなら、サイズ感や装丁による違いを比較できるから。表紙の素材や質感、色合いなどによって、受ける印象は実に様々だということがわかります。
続いて、表紙をめくっていきましょう。社史の中に目を移すと、
・縦書きor横書きによるイメージの違い
・デザイン
・色づかい
・写真やイラスト、図解の使い方とボリューム感
・特色のあるコンテンツ
など、社史づくりをする上でのヒントもたくさん発見できます。
3.3. 業種ごとの特徴も丸わかり
社史コーナーでは業種ごとに社史が分類されているので、「○○業に関わる会社の社史を調べたい」といったときでもスムーズに調査できます。
おすすめの探し方は以下の通りです。
②書架自体にも表示があるので、照らし合わせながら探す
また、同じ業種に属する会社の社史もまとめて見られます。同じ業種に関わる会社の社史を見比べていくと、好まれるテイストやコンテンツなど、その業界ならではの特徴が読み取れるでしょう。
なお、ここでは一点注意も必要です。公式サイトによると、図書館で行っている分類は、創業時の業種を当てはめているとのこと。中には、
・業種の多角化を図った
といった理由で他の業種に分類されている場合もあるようです。また、同じ業種でも他のところに分類されているケースもあるのだとか。そのため、現在持たれている会社のイメージと、実際の社史の分類が異なる場合も考えられます。
もし目当ての会社の社史がすぐに見つからない場合は、検索機OPACを使って保管場所を調べるようにしてください。「△△業かな…□□業かな…」と自分で歩き回りながら探すよりも、スピーディにたどり着けるでしょう。
3.4. 同じボリューム感の社史からヒントを得る
社史といっても、10年史、50年史、100年史などまとめている歴史の長さは社史によって異なります。神奈川県立川崎図書館では数多くの社史を保有しており、様々なボリュームの社史が閲覧できます。ぜひ、制作しようとしている社史と同じボリューム感のものを見るようにしてください。構成や、コンテンツそれぞれのボリューム感など、参考にできる部分も多いはずです。
4. 社史コーナー周辺で注目しておきたいスポット

社史コーナーをひと通り確認したら、次はまわりを見渡してみましょう。このエリアは、単に書架に社史を並べているだけの空間ではないことがわかります。神奈川県立川崎図書館では、社史のさらなる活用を目指した、様々な取り組みも行われているようです。ここでは、社史コーナー周辺で注目しておきたいスポットを紹介していきます。
・新着社史コーナー
・検索機能OPAC
・社史関連コーナー
いずれも、訪れた際はぜひチェックしておきたいスポットばかりです。では、それぞれ見ていきましょう。
4.1. 社楽コーナー
公式サイトでも公開されており、本記事でも紹介した「社楽」ですが、ここ社史コーナーの一角では社楽の紙面と共に、社史の実物の展示が行われています。実際に本物の社史を眺めながら記事を読めるため、まるで博物館を訪れた時のような気分が味わえるでしょう。
展示ケースの横には、社楽のバックナンバーが収められたファイルが置かれており、気軽に手に取って読めるようになっています。「社楽を読んで予習してくるのを忘れた!」という人は、この機会にぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。社史の魅力を堪能することができます。
4.2. 新着社史コーナー
社史コーナーの入り口付近にある3段ラックには、新着社史がまとめて置かれています。その名も「新着社史コーナー」。ここに集められている社史は比較的最近のものが多いため、トレンドなどつかみやすいかもしれません。「イマドキ」の要素を取り入れたいときにおすすめです。
また、あらゆる業種の社史が同じところに集まっており、気軽に手に取りやすい雰囲気にもなっています。異業種の社史をヒントにしたいときにも役立つでしょう。
4.3. 蔵書検索OPAC
社史を探したいときにサポートしてくれるのが、この蔵書検索OPACという検索機です。
館内には全部で3か所設置されています。そのうちの1台は社史コーナーのすぐ横に設けられているため、社史を調査する人にとっても大変便利。分かりやすいマニュアルが置かれており、初めて操作する際も安心です。
検索結果からは、探している社史の配架場所や貸出状況といった情報が確認できます。社史で探しものをする際は、蔵書検索OPACをうまく活用すると効率よく進めていけるでしょう。
4.4. 社史関連コーナー
社史コーナーの通路を挟んだ向かい側には、社史関連本コーナーがあります。それほど数は多くありませんが、ここには、社史のつくり方やヒントとなるような本も並んでいます。
・社史制作を進める中で疑問点が出てきた
といった場合には、ここを訪れると何らかのヒントを得られるかもしれません。一度は足を踏み入れておきたい場所と言えます。
5. いよいよスタート!おすすめの調査場所を紹介

社史コーナーや周辺エリアをまわり、じっくり調べていきたい社史が見つかったら、閲覧コーナーを利用して調査しましょう。館内にはいくつか閲覧スペースが設けられており、館内で調査したいときでも大丈夫です。ここでは、おすすめポイントなども交えながら紹介していきます。
5.1. 一番のおすすめは「社史」調査優先席
社史を調査するのであれば、やはり一番のおすすめスポットは「社史」調査優先席。社史コーナーの中にある、4人掛けのデスクです。2人ずつ向き合うようなスタイルとなっていますが、真ん中には透明の間仕切りがあり、感染症対策も◎。おすすめポイントは、以下の3つです。
・まわりがとても静かで集中しやすい
・電源がありパソコンが使用できる
社史がすぐ手に取れる距離にあり、何よりもそこが最も評価したいポイント。デスクの脇には、コピーを希望する際に必要な複写申込書や自由に使える「しおり」も置かれています。まさに社史の調査、研究をするために最適な場所です。
5.2. 集中しやすい環境のカウンター席
二番目におすすめしたいのは、窓際に配されたカウンター席です。席数は全部で24席。社史コーナーから離れた場所にありますが、気になった社史1冊をじっくりと読みこみたいような場合に向いているでしょう。ではさっそく、こちらのおすすめポイントをお伝えしていきます。
・電源がありパソコンが使用できる
カウンタータイプで窓に向かって座るスタイルのため、目の前を人が横切って集中しにくい、といった心配もありません。両サイドには半透明の間仕切りが設けられており、隣の人との境界もしっかり作られています。その環境の良さからか、人気の閲覧スペースとなっているようです。
5.3. 他にもこんなに!館内の閲覧スペース
社史調査優先席は席数が限られており、カウンター席は人気の閲覧スペース。そのため、「せっかく訪れても、じっくり調べられる場所がなかったらどうしよう…!」という不安を抱くこともあるでしょう。しかし館内にはこれら以外にまだ閲覧スペースがつくられており、安心して利用できます。
・臨時閲覧スペース
総合カウンター前にある閲覧スペースには、6人掛けのデスクが3つほど並んでいます。入口から最も近い閲覧スペースなので、入館した際に気が付きやすいでしょう。隣には「調査研究」優先席というデスクもありますが、こちらは利用する際にカウンターへの申し出が必要なようです。
また、館内の一番奥にあるカンファレンスルームは、臨時閲覧スペースとして開放されている場合もあります。「臨時」なので、訪れるタイミングによって利用可否は変わるでしょう。社史コーナーからもわりと近い場所に位置しているため、もし開放されているときは一度チェックしてみてください。
5.4. Wi-Fiも整っていて充実した環境
神奈川県立川崎図書館ではFREE Wi-Fiのサービスを提供しており、インターネットへの接続も可能です。社史を調査する場所として、十分に環境が整っている図書館だと言えるでしょう。
6. 神奈川県立川崎図書館の利用方法
ここでは、神奈川県立川崎図書館の利用方法を説明していきます。
6.1. 閲覧したいとき
閲覧は誰でも自由に行うことが可能で、利用資格なども設けられていません。もちろん、社史コーナーに関しても同じです。これは、神奈川県立川崎図書館が持つ最大の魅力とも言えるのではないでしょうか。
6.2. 借りるとき
図書を借りたい場合は、他の図書館と同じような流れになります。まずは、利用登録を行いましょう。
ただ、利用登録をして図書館カードを発行できるのは、県内在住・在勤・在学のいずれかに該当する必要があります。また、手続きを行う際には、本人確認ができる書類の提示が必要です。在勤・在学の場合は、所属が確認できる書類も求められるため、忘れずに持って行きましょう。なお、登録手続きは館内にある総合カウンターの他、郵送でも行うことができます。
図書は10冊まで貸出可能で、貸出期間は3週間です。ただし、所蔵されている図書の中には、「貸出不可」となっているものや、雑誌など一部貸出対象外の資料もあります。
6.3. 返すとき
返却は、館内にある総合カウンターで行います。閉館時に、図書館入口にあるブックポストに投入する方法もありますが、社史に関してはこのサービスの対象外となっているようです。
必ず開館時間内に直接総合カウンターに持って行くようにしてください。
6.4. コピーしたいとき
有料にはなりますが、図書のコピーを取ることができます。希望する場合は「複写申込書」に必要事項を記入してから、スタッフへ申し込んでください。コピー作業はセルフとなっているため、申し込み後、館内に設置されているコピー機を使って行います。
なお、コピーができるのは著作権法第31条で認められている範囲で、調査研究のため以外に使用することは禁じられています。取扱いには注意しましょう。
6.5. 相談したいとき
図書館司書に、図書館資料や資料研究に関する相談も可能です。なお、社史コーナーの近くには専門相談カウンターが設けられていますが、タイミングによっては担当者が不在にしている場合もあります。そのような場合は、総合カウンターで尋ねるようにしてください。
6.6. 注意しておきたいポイント
利用する上での一般的なマナーは、他の図書館と基本的には同じです。せっかくなので、ここで一度おさらいしておきましょう。NGな行動としては、以下のことが挙げられます。
・閲覧席の利用時、荷物や資料を置いたままでの長時間離席
もちろん、図書館なので静かに過ごすことも忘れないようにしたいものです。そのため、例えば以下のような面にも配慮する必要があります。
・ヘッドホンやイヤホンからの音漏れ
なお、水分補給する際は、ペットボトルや水筒など口の閉まるもののみ使用OKとしているようです。お互いにルールを守って、誰もが快適に過ごせる空間にしていきましょう。
7. 神奈川県立川崎図書館は長時間滞在時でも安心

日本屈指の社史保有数を誇る神奈川県立川崎図書館。せっかく訪れたのに、短時間で済ませてしまってはもったいないです。一方で、気が付いたらあっという間に時間が経っており、「一度休憩を挟みたい」といったケースもあるでしょう。
もし長時間滞在するときでも、ここなら安心。神奈川県立川崎図書館はかながわサイエンスパーク(KSP)の2階にあり、同じ建物の中にはコーヒーショップやレストラン、コンビニなどの店舗も入っています。雨の日でも濡れずに移動できるため、とても便利でしょう。
長時間調べものをして疲れたら、コーヒータイムを挟んでリフレッシュし、また図書館へ戻る…といった過ごし方もおすすめ。思う存分、社史コレクションを堪能できそうです。
8. 社史コレクションはこんな人にもおすすめ!
神奈川県立川崎図書館「社史コレクション」がおすすめなのは、以下のような人です。
・会社の歴史を深掘りしたい人
・社史の調査をしている人
8.1. 社史担当者
社史づくりの担当になったら、一度はここの社史コレクションを訪れておきたいもの。神奈川県立川崎図書館のように、誰でも自由に約22,000冊もの社史を閲覧できる図書館は、とても貴重な存在です。
利用するメリットとしては、
・他の業種の会社が発行した社史を閲覧できる
・現在の社史のトレンドを調査できる
・特色のあるコンテンツを発見できる
などが挙げられます。社史をつくる上で多くのヒントを得られるのではないでしょうか。
8.2. 会社の歴史を深掘りしたい人
「○○会社の歴史を深く探っていきたい」というようなケースでも、社史コレクションはおすすめです。具体的には、
・クライアントである会社の歴史を深掘りしたい
といった人が当てはまるでしょう。
このようなケースの場合、ある特定の会社に絞って調査する形になります。公式サイトではキーワードなどを元に図書の検索が行えるため、所蔵の有無や状態などをあらかじめチェックしてから訪れる方がよいかもしれません。
8.3. 社史の調査をしている人
社史の調査をしている人にとって、社史コレクションは欠かせない存在です。そして、社史コレクションの他に、もう一つおすすめしたいポイントもあります。
それは、神奈川県立川崎図書館で定期的に開催されている「社史フェア」。初めて開催されたのは2014年で、その後はだいたい一年に一度くらいのペースで企画されているようです。約200冊の社史が展示されており、たくさんの社史に出会うチャンスでもあります。開催期間は数日間と決して長くはありませんが、社史の調査をする場合はぜひチェックしておきたいイベントでしょう。
ちなみに、筆者が訪れたタイミングは、社史フェアの会期中ではなかったのですが、館内の一角で「2024年の社史フェアで展示された社史」が展示されていました。コメントとともに社史が紹介されているため、注目すべきポイントもわかりやすく、とても興味深かったです。
9. 社史が完成したらぜひ寄贈してみよう
社史づくりが完成したら、今度はぜひ資料を寄贈してみましょう。寄贈がおすすめの理由や、寄贈方法について説明していきます。
9.1. 寄贈で開かれる未来
社史は一般的な本とは異なり、販売されておらず、発行部数や配布先も限られていることが多いです。そのため手に入れることが難しく、コレクションをより一層充実させるためには「寄贈」という手段が欠かせなくなっています。
それぞれの会社の歴史を残し、また未来へとつないでいくためにも、社史づくりを行ったら寄贈を検討してみてはいかがでしょうか。神奈川県立川崎図書館の社史コレクションを訪れると、やはりその保有数の多さに驚かされます。そしてそれは、社史に関する調査や研究への大きな手掛かりとなり得るもの。寄贈を通し、その一端を担うことができるのです。
9.2. 神奈川県立川崎図書館へ寄贈する方法
寄贈できる社史は、すでに所蔵されていないものに限られています。汚損や破損、書き込み、カビがある…など、劣化したものも当然ながら対象外です。また、寄贈を申し出る際は、受入の可否や配架場所など、図書館側に一任する事項もいくつかあるため、事前に確認しておきましょう。書架スペースの事情や処分費用など、様々状況を踏まえつつ、厳選した上で選定し、寄贈を受入れているようです。
寄贈を申し出る場合、まずは以下のことを行っておきます。
・寄贈を申し出に関し、事前に電話やメールなどで連絡
・寄贈申込み資料のリスト作成と提示
事前に連絡せずに社史を送付しても、返送されてしまう場合があるようです。まずは相談から始めるようにしましょう。
なお、寄贈の受入れ方法には、
・郵送などでの送付(送料は申出者の負担)
という二種類があります。
10. まとめ
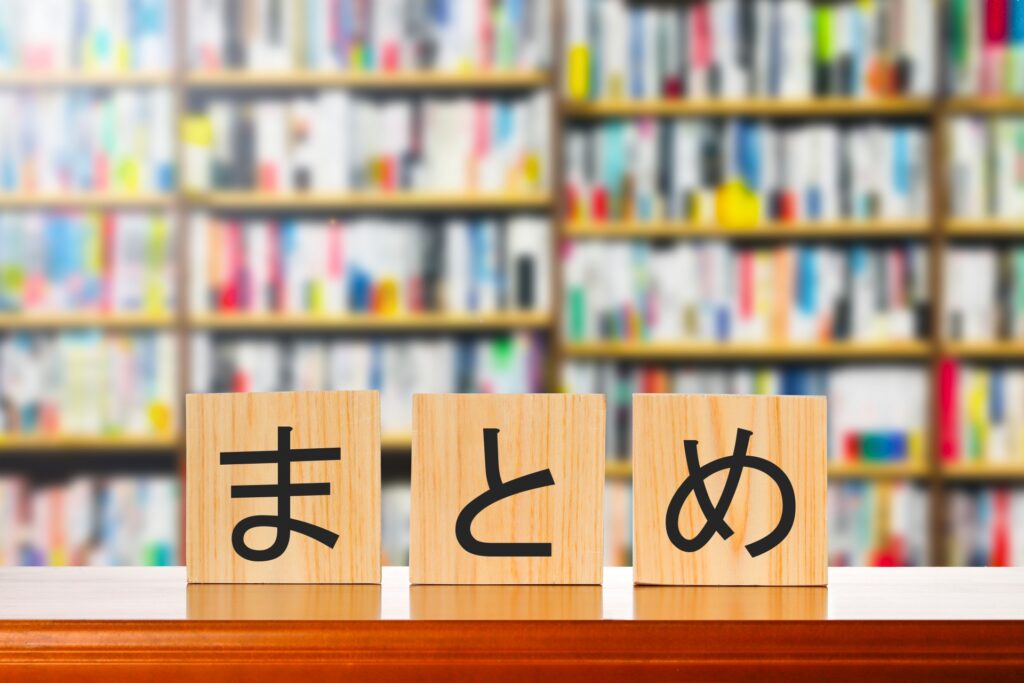
本記事では、神奈川県立川崎図書館「社史コレクション」の魅力や利用方法などについて、詳しく紹介していきました。
社史担当者になり、「ここの社史コレクションが気になっていた」「初めて利用を考えている」という人も、安心して訪れられるようになったのではないでしょうか。
様々な発見や驚きが得られる、神奈川県立川崎図書館の「社史コレクション」。上手に活用しながら、魅力的な社史づくりを行っていきましょう。
URL:https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/
